勉強を習慣にするメリット
 |
自分の意志で勉強を継続するのは困難です。学生のうちはまだしも、社会人になると注意やサポートをしてくれる人が少なくなり、ついサボってしまうこともあります。そこで、勉強を日々の習慣として取り入れることをお勧めします。 勉強を習慣化することには、以下の二つのメリットがあります。 |
・勉強を自然に進められる
 |
勉強が日々の習慣となると、自然に机に向かう習慣が身につきます。「勉強しなければ」という強い意識がなくても、身体が自動的に勉強の姿勢をとるようになります。 勉強が習慣化されていない場合、机に向かうことが面倒に感じることがあります。特に、やる気が出なかったり疲れているときは、さらに難しく感じることもあります。 しかし、日常生活の一部として勉強を習慣づければ、少しやる気が出なくても勉強を始めることが容易になります。実際に手を動かしているうちに、徐々に気力が回復し、通常通りの勉強を続けることができるようになります。 勉強を気分やタイミングに合わせて行うスタイルでは、始めるまでのハードルが高くなりがちです。 |
・努力の積み重ねで自信が持てる
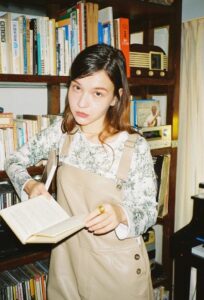 |
勉強を習慣化することは、自信を高める大きなメリットがあります。毎日決まった時間に勉強を続けることで、少しずつ着実に学習が進んでいきます。 決めた勉強ルールを守り、実力の向上を実感することが、「自分は頑張れている」との自信へと繋がります。 一つのことを長期間続けるのは容易ではありませんが、勉強は知識だけでなく、忍耐力や行動力も養います。勉強の習慣が身についたとき、自己評価が高まり、自己肯定感が向上することでしょう。 |
勉強を習慣化するには?
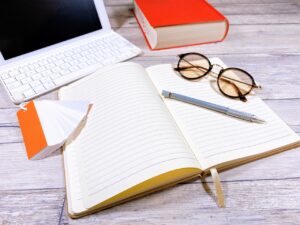 |
勉強を習慣化することで、始める際の抵抗が軽減し、勉強効率が向上することが明らかになりました。しかし、習慣化するまでが一つの課題となります。 勉強を習慣にするためには、いくつかの有効なコツがあります。以下に示す三つのポイントを押さえ、ぜひ明日から実践してみてください。 |
・勉強する時間・場所を決めておく
 |
勉強を習慣化するためには、事前に勉強する時間と場所を決めることが重要です。気分や状況によって勉強場所や時間を変更していると、習慣化が難しくなります。 例えば、「毎日夜8時には机に向かう」「水曜日には特定の科目を集中して学習する」「週末には図書館で問題集の過去問を一通り解く」といった具体的なルールを設定し、繰り返し実践することが効果的です。行動パターンが定まることで、勉強は自然と習慣となります。 ルールを決定するためには、まず全体のスケジュールを立てることが必要です。資格試験や社内テストなどの期限が決まっている目標に対しては、逆算して「何をいつまでに勉強すべきか」を計画しましょう。目標を基に計画を立てることで、1日に必要な勉強時間が明確になります。 |
・始めるときのスイッチを決める
 |
勉強を習慣化するためのコツは、「勉強を始めるスイッチ」を設定することです。例えば、「参考書を開く」「リスニングを開始する」といった具体的な行動を決めておきます。このスイッチとなる行動によって、気持ちを勉強モードに切り替えるのです。 紅茶やコーヒーを飲む、あるいはチョコレートや飴を一つ食べるといった小さな儀式でも構いません。「この行動をとった後は必ず勉強する」といったルーティンを確立することで、勉強の習慣化がスムーズになります。 |
・時間になったら必ず始める
 |
勉強を習慣化するためのもう一つのコツは、決まった時間になったら必ず勉強を始めることです。決まった時間が来たら、たとえ他のことをしている最中でも、すぐに勉強に取りかかりましょう。 「読みかけの本が面白いから」「小腹がすいたので食事を先に…」などの理由で勉強を先延ばしにすると、次第に勉強を始めるのが億劫になってしまいます。 時間が来たからといって、いきなり本格的な勉強を始める必要はありません。初めは問題を2〜3問解いたり、数分間だけ単語を暗記したりするなど、軽い内容から取り組むだけでも構いません。いったん勉強を始めることで、自然とハードルが下がり、やる気が出てくるでしょう。 |
・勉強を続けるコツ
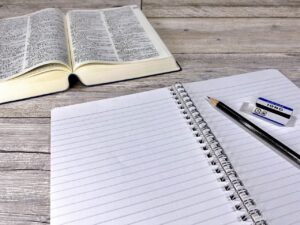 |
勉強の習慣を身につけるために毎日努力していても、「つい怠けてしまうかもしれない」と不安に感じることがありますよね。サボりがちな方がしっかりと勉強のペースを確立するためには、どのような工夫が必要でしょうか? |
・まずは小さく目標設定
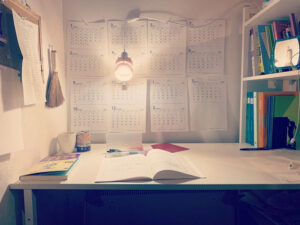 |
勉強の目標を「1年後の資格試験合格」や「半年で参考書を10冊マスターする」といった大きなものに設定してはいませんか?目標が大きく、達成までに時間がかかると、途中でモチベーションが低下しがちです。 まずは、小さな目標を設定し、達成可能な範囲で取り組むことをお勧めします。例えば、「1日1ページ参考書を読む」「1日に1問だけ過去問を解く」といった、無理なく確実に達成できる目標を設定しましょう。 自分が続けられる最低限の目標を立て、それを1週間続けるごとに時間や勉強量を少しずつ増やしていく方法が効果的です。このアプローチにより、挫折することなく勉強を続ける自信がつき、それが勉強を習慣化するための意欲となります。 |
・どうして勉強するのか再確認
 |
勉強のやる気が失われ、怠けてしまいそうなときには、「なぜ自分は勉強しようと思ったのか?」を改めて確認してみてください。目標をしっかり意識できていないと、勉強そのものが目的となり、次第に勉強が苦痛に感じることがあります。 例えば、資格取得が勉強の目的であれば、「資格を取得してキャリアアップする」「長年希望していた○○の職に就く」といった具体的なゴールがあります。勉強の結果、自分がどのようになりたいのかを思い出すことで、再びやる気が湧いてくるでしょう。 |
・周りの目を利用するのもアリ
 |
どうしても怠けてしまいそうなときは、周囲に人がいる環境で勉強するのがおすすめです。勉強の手を止めたくなっても、真剣に勉強している人が視界に入るだけで、サボることに対する躊躇が生まれます。 図書館や勉強可能なカフェ、コワーキングスペースなど、他の人も勉強している環境では怠けにくいです。外出が難しい場合は、同僚がいる会社の休憩室や家族がいる家のリビングも有効です。 周囲に誰かがいると、まるで監督されているかのような感覚を持ち、良い意味でのプレッシャーを感じることができます。意志が弱いと感じる方は、ぜひ人がいる場所を積極的に活用してみてください。 |
社会人が勉強するときに注意したいこと
 |
社会人が勉強をする際は、学生とは異なる条件が多くあります。自由に使える資金は増える一方で、仕事の忙しさにより勉強の時間を確保するのが難しくなることもあります。社会人が勉強する際に注意すべきポイントを以下にご紹介します。 |
・セミナーはよく考えてから
 |
社会人が勉強する際は、教師がいないため、学ぶ内容や方法を自分で決定する必要があります。しかし、漠然と「良さそうだから」という理由でセミナーに参加するのは避けるべきです。 セミナーに依存してしまうと、講師の話を受け身で聞くだけになりがちです。セミナーは、勉強が行き詰まり、自力では解決が難しくなったときに検討するのが理想です。 もちろん、質の高いセミナーも多く存在します。勉強に困難を感じた際には、セミナーを有効に活用するのも良い方法です。セミナーに参加する前には、自分にとって本当に必要な内容であるかどうかをしっかりと見極めてから決定しましょう。 |
・睡眠時間はなるべく削らない
 |
社会人は多忙なため、勉強時間を確保するのが難しいですが、睡眠時間を削って夜中まで勉強するのは推奨できません。睡眠が不足すると、昼間の集中力が低下し、仕事や勉強の意欲も減少してしまいます。 また、寝不足が続くと体調を崩しやすくなり、結果的に勉強の効率も悪化します。 どうしても勉強時間を確保したい場合は、睡眠時間を削るのではなく、寝る時間や起きる時間を調整して朝型の勉強スタイルに切り替えるのも一つの方法です。 人それぞれに必要な睡眠時間や、集中しやすい時間帯は異なります。自分の体調や集中力を考慮しながら、自分に最適な勉強スタイルを見つけてください。 |
コツをつかんで勉強を習慣に
 |
社会人が勉強を続けるためには、自然に机に向かう習慣を身につけることが重要です。日常生活の一部として勉強を取り入れることで、やる気が出ない日でも勉強に取りかかりやすくなります。 時間や場所を決めてルーティン化することや、勉強を始めるスイッチを設定するのが効果的です。怠けがちな場合は、小さな目標を設定し、それを一つずつ達成するよう心がけると良いでしょう。 最初は進展が遅く感じるかもしれませんが、コツを掴むことで勉強を続ける力が身につくはずです。 |